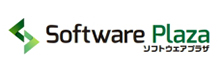書籍版「建設ITガイド」に掲載した特集記事のバックナンバーです。
-
2024.07.29
海外におけるBIM動向 BIM情報マネジメント国際標準ISO19650におけるopenBIMの役割とは
-
2024.07.22
「維持管理」新時代の到来見えてきた課題に対して、新技術を導入して試すことが最初の第一歩
-
2024.07.17
土木におけるAI活用の現状と将来
-
2024.07.17
新潟県中山間地域発!建設DXチャレンジ事例雪深い地域の受注の半数が下請け工事である小さな会社が進める建設DXとは?
-
2024.07.12
BIM/CIM原則適用における設計・施工BIM/CIMの留意点
建設コンサルタント・建設会社のBIM/CIMを支援してきたMalmeが見ている原則適用下での留意点や内製化に悩む組織について共有します -
2024.07.08
地方発!建設DXチャレンジ事例中小企業による次世代のICT施工に向けた展望と取り組み
-
2024.07.04
自治体における建設DX―広島デジフラ構想とDoboXの構築―
-
2024.07.02
BIM人材育成の指針・目標となる新たな資格制度「BIM利用技術者試験」の創設
-
2024.07.02
官庁営繕におけるBIM活用の取り組み
-
2024.07.02
BIM積算の現状と課題
最近の記事
- 自治体におけるBIM活用事例|八幡市役所-BIMFMによる庁舎管理の省力化-
- 実技試験の開始で本格始動した「BIM利用技術者試験」制度
- 「建築仕様書の研究」から「BIM時代の建築仕様書」へ
- 大学のBIMセンターと産官学連携からみた台湾のBIM技術者育成
- 地方ゼネコンによるBIM活用の取り組みと展望-BIM連携の活用でパートナーシップの強化を目指す-
- 鉄筋工事におけるBIMを適用したワークフロー
- 大阪・関西万博工事のBIM活用-建設事業の情報基盤としてのBIMの成熟とその後の「あるべき姿」を目指して-
- 沖縄総合事務局におけるBIM/CIMの取り組み
- 建築BIM推進会議における検討や建築BIMの推進に向けた取り組みの状況について
- 「BIM概算ガイドブックI」の発刊について-BIMデータとコスト情報の融合によって生まれる新たな可能性-
過去記事
-
2013
- 11月 (1)