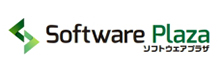書籍版「建設ITガイド」に掲載した特集記事のバックナンバーです。
最近の記事
- 自治体におけるBIM活用事例|八幡市役所-BIMFMによる庁舎管理の省力化-
- 実技試験の開始で本格始動した「BIM利用技術者試験」制度
- 「建築仕様書の研究」から「BIM時代の建築仕様書」へ
- 大学のBIMセンターと産官学連携からみた台湾のBIM技術者育成
- 地方ゼネコンによるBIM活用の取り組みと展望-BIM連携の活用でパートナーシップの強化を目指す-
- 鉄筋工事におけるBIMを適用したワークフロー
- 大阪・関西万博工事のBIM活用-建設事業の情報基盤としてのBIMの成熟とその後の「あるべき姿」を目指して-
- 沖縄総合事務局におけるBIM/CIMの取り組み
- 建築BIM推進会議における検討や建築BIMの推進に向けた取り組みの状況について
- 「BIM概算ガイドブックI」の発刊について-BIMデータとコスト情報の融合によって生まれる新たな可能性-
過去記事
-
2013
- 11月 (1)