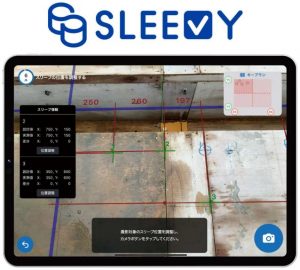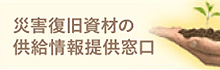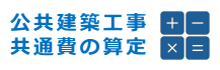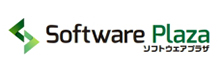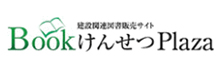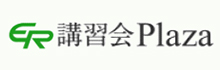書籍版「建設ITガイド」に掲載した特集記事のバックナンバーです。
-
2025.06.09
i-Construction 2.0をはじめとしたインフラ分野のDX展開の取り組み
-
2025.05.23
BIMオブジェクト標準とBIMライブラリ技術研究組合の活動
-
2025.05.23
地方発! 建設DXチャレンジ事例「DXは難しくない!」若手による意識変革で建設DXが次々に実現
-
2025.05.23
BIM/CIMによる設計と施工の連携― 設計の3Dモデルは施工で活用できるか? ―
-
2024.09.19
建築学科における情報技術の教育における課題と展望
-
2024.09.10
BIMで積算が変わる!-BIM連携積算への取り組みと双方向連携への実現に向けて-
-
2024.09.02
NTTファシリティーズの「ライフサイクルBIM」戦略 既存多施設のライフサイクルマネジメントへのBIM導入
-
2024.08.27
中堅ゼネコンにおけるBIM推進正確に自動化されたシステムがBIM省力化のパートナーに
-
2024.08.26
BIMを超えた建設DXの実現とデジタルデータの標準化
-
2024.08.19
生成AIによる建築デザインの可能性 建築設計アシストAIツール「AiCorb」の開発を通して
最近の記事
- 自治体におけるBIM活用事例|八幡市役所-BIMFMによる庁舎管理の省力化-
- 実技試験の開始で本格始動した「BIM利用技術者試験」制度
- 「建築仕様書の研究」から「BIM時代の建築仕様書」へ
- 大学のBIMセンターと産官学連携からみた台湾のBIM技術者育成
- 地方ゼネコンによるBIM活用の取り組みと展望-BIM連携の活用でパートナーシップの強化を目指す-
- 鉄筋工事におけるBIMを適用したワークフロー
- 大阪・関西万博工事のBIM活用-建設事業の情報基盤としてのBIMの成熟とその後の「あるべき姿」を目指して-
- 沖縄総合事務局におけるBIM/CIMの取り組み
- 建築BIM推進会議における検討や建築BIMの推進に向けた取り組みの状況について
- 「BIM概算ガイドブックI」の発刊について-BIMデータとコスト情報の融合によって生まれる新たな可能性-
過去記事
-
2013
- 11月 (1)