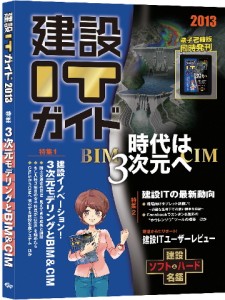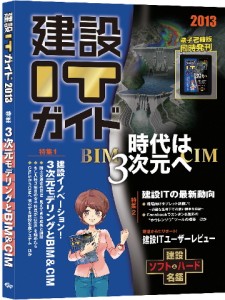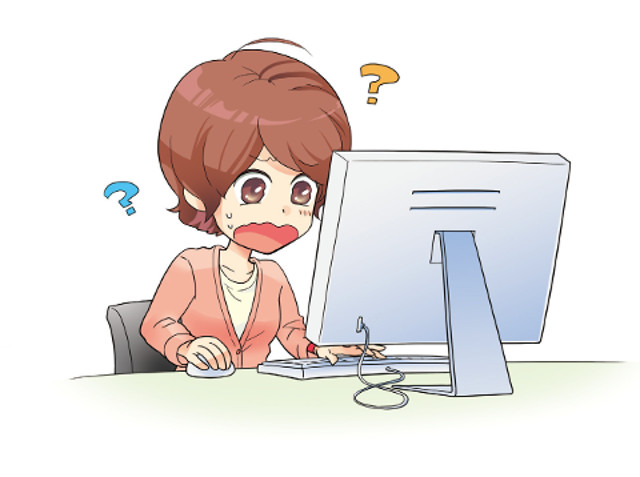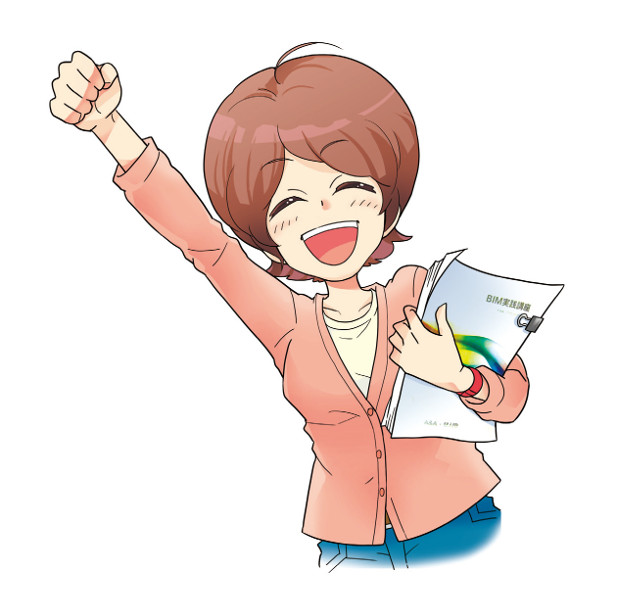株式会社 山設計工房
BIM導入前夜

私が勤務する事務所は集合住宅の意匠設計を主な業務としている。
会社規模はそれほど大きくないものの、延床面積1万㎡超のプロジェクトを扱うこともしばしばある。
2011年まで私が使っていたCADは1998年発売のVectorWorks ver.8。
私が入社するずっと以前から先輩たちがおよそ14年間愛用し続けてきたソフトだ。
そんなわが社の歴史と伝統が詰まったソフトを駆使して日々の仕事に励んでいたが、時折不都合があった。
高いバージョンのCADを使用している協力事務所とのデータのやり取りに手間がかかる(その度に相手方にバージョンを下げてもらう必要がある)、着色やハッチングといった図面表現の機能が乏しいため力技による図面レイアウトを行うこともしばしば…操作感に多少のストレスを感じてはいたものの、業務上は致命的な問題とまでは至らず、「まあこんなものかな、まだこのソフトも十分使えるかな」と少しの不都合を感じながらも仕事に励んでいた。
図面データが開けない!
2011年の秋、苦心の末にプロポーザルで勝ち取った某団地建て替えのプロジェクトで、それまでの「些細な不都合」が突然「致命的な問題」へと変わってしまった。
敷地面積が数ヘクタールと広大なその団地は、既に先行して他の複数の街区が建て替えられており、他の設計事務所がそれらの膨大なデータを統合した配置図を作成していた。
そのデータを引き継いで、いざ業務に取り掛かろうとした時だった。
データが開かないのだ。
大容量のそのデータは同じVectorWorksで作成されていたもののバージョンが遥かに高く、データを作成した設計事務所にバージョンを下げてもらおうにもver.8まで下げることはできなかった。
それならば、とDXFデータに変換してもらったのだが、変換したことによりデータ容量がさらに大きくなってしまい、当時使用していたスペックのPCは完全にフリーズ。 仕事に支障が出るというレベルではない。
このままでは仕事ができない。
とうとう私たちは、膨大な容量のデータが動くハイスペックなPCと最新版のソフトを購入せざるを得ない状況に追い込まれてしまった。
…BIM?
上司の指示で、最新のPCとソフトの現状についてすぐに情報収集を始めた。
特にソフトについてはメーカーのホームページを隅々まで調べた。
「クリエイティブな2D表現力」「縮小された取り込み時ファイルサイズ」などなど…そこには私が日々少なからず不都合に感じていたことを丸ごと解決してくれそうな心躍る魅力的なフレーズと画像がいくつも並んでいた。さらに上位製品になると美しいパースも描け、BIMも使えるそうだ。
…BIM?
3つのアルファベットによる見慣れない単語が目に飛び込んできた。
読み進めると「スラブツール」「壁オブジェクト」「窓オブジェクト」といった機能が搭載されているようなのだが、なんだかよくわからない。
気になったので今度はインターネットで「BIM」なるものを調べ始めた。
Wikipediaから始めて建設ITまでたくさんのサイトを見たけれど、なんとなくわかったような、わからないような…ひとつだけ確かなのは、どうやら「BIM」は「ビム」と読むらしく、ここ数年で日本でも普及し始めているそうだ。
先輩、BIMって知ってます?
新しモノ好きな私は一気に興味が湧いたので、インターネットで集めた資料を持って先輩のもとへ駆けつけた。
先輩にもBIMに興味を持ってもらい、一緒に上司を説得してBIM機能を搭載したソフトを導入してもらおうと考えたのだ。
「先輩、BIMって知ってます!?」
かき集めた資料を手に何とか先輩に理解してもらおうと一生懸命説明した。
しかし私自身がBIMをしっかり理解しておらず、断片的な知識しかないため説明はしどろもどろ。
それでも先輩は黙って最後まで説明を聞いてくれて、最後に一言ポツリと言った。
「要するに、BIMというのはPCの中で仮想の建物を実際と同様につくるという概念なんじゃないかな」
「複雑な構成の建物を設計する場合なら有効かもしれないけど、僕らが設計するシンプルな構成の建物には必要ないんじゃないかな」
と、冷静かつ否定的な感想が返ってきた。
私自身がきちんと理解できていないのだから、先輩に興味を持ってもらえるような説明ができるはずがない。
しばらく考えて、意を決してVectorWorksを取り扱うエーアンドエー社に電話した。
餅は餅屋だ。
自分で調べて人に説明するよりも、メーカーの方に分かりやすく説明してもらって本物のBIMを見せてもらった方がはるかに理解しやすいはずだし、先輩や上司にも同席してもらえば同じ情報を共有できる。
BIMに興味があり導入を検討している旨を電話口で伝え、BIMの説明とソフトのデモンストレーションをしてもらえないかお願いしたところ、快諾してくれた。
ツールを求めて
数日後、エーアンドエー社の担当者の方に来所いただき、先輩と上司にも同席してもらった。
BIMについての知識はほぼゼロであることを伝え、BIMとは何か、BIMで設計することでこれまでと何が変わるのか、どのようなメリットがあるのか、といった内容で、分かりやすい初心者向けのプレゼンテーションをしていただいた。
BIMとCADの違いに戸惑い
BIMはCADと異なり「線を引く」のではなく、柱や壁を「立てる」、窓を「取り付ける」ことで3次元空間に建物を建設し、そこから図面を作り出すことが分かった。
これまで使っていたCADとはまるで違う概念であることに正直かなり戸惑った。
本当に私たちに使いこなせるのか…不整合の回避やプロジェクト初期段階でのパース確認といったBIMのメリットに対して大きな魅力と可能性を感じつつ、同時に不安も大きくなっていった。
先輩も同じ不安を持っていたのだろう。
BIMで設計を進めていて途中で挫折してしまった場合はどうなるのか、一度BIMで設計を始めたら詳細図レベルまでBIMでやり切らなければならないのか、と矢継ぎ早に質問していた。
確かに、慣れないBIMで設計を始めてしまったがばかりに、もし途中でうまくいかなくなってBIMを諦めざるを得ないことになってしまったら、もう一度これまでのCADでやり直すことになってしまうのか…?そう考えるとBIMを導入することがリスキーなことに思えてきてしまった。
しかし、メーカーの方がおっしゃった一言でその不安は解消された。
「全ての図面をBIMで作成する必要はありません。3次元モデルを基にこれまでと同じように2次元で作図することができますよ」
それを聞いて先輩も安心したようだ。最初は無理をせず、少しだけBIMを取り入れてみる。
慣れてきたら少しずつBIMの割合を増やしていくことができる(これを「BIM度を上げる」と表現されていた)。
つまり私たちのペースで、私たちのやり方でBIMに取り組むことができ、私たちなりのBIMを目指していけば良いのだ。
途中で3次元から2次元へ移行できるということが大きな安心につながり、BIM機能を搭載したVectorWorksを購入することで満場一致した。
ワクワクとドキドキ
BIM導入を決めた時、もう少し待てばさらに新しいバージョンが発売される状況だった。
「どうせなら少しでも新しいものを」という上司の言葉もあり、発売までBIMは少しお預けとなった。
発売までBIMについての興味がどんどん膨らみ、ネットや書籍で周辺情報をあれこれ夢中で調べた。
BIMを華麗に操り、どんどん図面を作る自分を妄想していたのだが、調べていくとひとつ気付いたことがあった。
メディアに登場するBIMを本格的に使って設計された建物の設計者を調べていくと、決まって一部の大手設計事務所の名前が目に付いた。
そのうちに「デモンストレーションではメーカーの人は簡単そうに操作していたけど、実はBIMはとても難しいんじゃないか?星の数ほどある設計事務所の中でも、BIM導入に成功しているのは一握りなのかもしれない…」そんな不安が少しだけ頭をよぎった。
大きな期待とほんの少しの不安を抱きながら、最新版のBIMソフトを手にし、慣れ親しんだVectorWorks ver.8に別れを告げた。
BIM入門
とにかく使ってみよう!

愛用のBIM実践講座
私が担当していた当時進行中のプロジェクトに含まれる自転車置場と小さな付属棟設計でBIMを試してみることにした。
エーアンドエー社のホームページから事前にダウンロードしていたVectorWorksのためのBIM参考書『BIM実践講座』を横に置きながら、まずはRC壁式造の付属棟から始めた。
参考書の手順通りに壁ツールで壁を立てて、スラブツールで屋根を架けて、アクソメで確認しながら修正して…シンプルな形状だったので比較的スムーズにモデリングできた。
モデリングが終わるといよいよ図面を生成してみる。
こちらも参考書を見ながら平面図、立面図、断面図、ついでにパースも生成した。
思ったより簡単かも!
始める前の不安は吹き飛び、しばらくの間、意味もなく壁を動かしてみて、全ての図面が連動して自動に変更されていることに一人で驚き歓喜する私。
早速つまずいた!
ひとしきりBIMの基本機能を堪能したところで、次に自転車置場の設計に取りかかる。
こちらはS造で設備棟よりさらに小さかったのだが、ここで大きくつまずいてしまった。
参考書のモデルはRCの壁式造だったため、H鋼の柱や梁のモデリングの仕方が載っていないのだ。
インターネットで散々検索してみたものの、具体的な解説が載っているサイトは見当たらなかった。
困り果ててあれこれツールをいじって何とかH鋼を作ることができた。
実はさまざまな形状の鋼材が簡単に作れるツールがあるのだが、そのツールを知らなかったため、柱1本モデリングするのに結局半日かかってしまったのだ。
試行錯誤の末に、何とか自転車置場の平面図、立面図、断面図、パースを生成したが、このアウトプットに対する作業時間を考えるとそれぞれの図面を通常の2次元CADで描いてしまった方が早かったかもしれない。
部材をひとつずつモデリングし、必要ならば属性を与えていかなければならず、2次元CADで作図するよりも遥かに時間がかかるのだ。
とにかくそれが私の初めてのBIMで、残念ながらこの付属棟の計画は結局取り止めとなってしまったのだが、以降のプロジェクトでは部分的にでもBIMで設計するよう努めた。
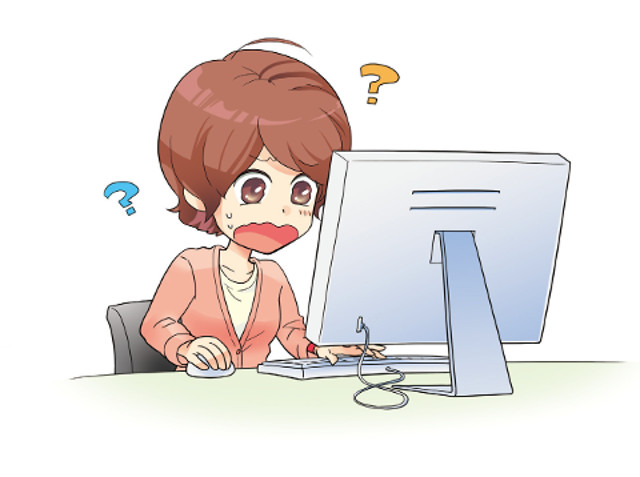
いよいよBIMを全面導入! ところが…
さまざまな機能を試しながら少しずつBIMに慣れてきた頃、新しいプロジェクトを担当することになった。
そのプロジェクトは延床面積5000㎡弱の比較的小規模の集合住宅だった。
いよいよ本格的にBIMで設計できるチャンスが来た!
上司と先輩に相談し、初めてプロジェクトの初期から全面的にBIMを導入してみようということになった。
この頃にはモデリングも大分スムーズに行えるようになり、図面とパースで確認しながらいくつも検討案を作った。
自分のスキルが確実に上がっていることをひしひしと実感しながらプロジェクトが進み、計画の大きな方針が決まってそろそろ構造や設備といった他の職種と調整する必要が出てきた頃に悩ましい問題が発生した。
私たちの事務所では意匠設計のみを行い、他の職種については外部の設計事務所に協力を仰いでいる。
協力事務所がBIMを導入していない場合、図面データ渡す際にDXFデータに変換する必要があるのだが、これがなかなかうまくいかないのだ。
DXF変換したはずのファイルを相手が開けなかったり文字化けしたりとまともな状態のデータを送ることができず、最終的にはデータを送付するたびに力技でBIMモデルを線データに壊すことで何とか送ることができた。
結局、このやりとりが手間になり、途中でBIMでの設計を諦めて2次元CADの設計に切り替えてしまった。
他職種の協力事務所とのやり取りが不可欠な私たちにとってスムーズなデータのやり取りができない以上、BIMで設計することが逆に足枷になってしまう可能性もあるかもしれない。
思いもよらない課題を突き付けられつつも、今もBIMのスキルアップに励んでいる。
新しい感覚
BIMの操作に慣れ始めてから感じている新しい感覚がある。
図面とパースがリアルタイムで連動することで検討案を複数作成する作業が格段に早くなった。
今までは2次元CADで図面を作成し、それを基に別ソフトでモデリングするというステップでパースを作成していたためパースを作るのに時間がかかったが、BIMはひとつのモデルからパースと図面を作るため、これらを同時に生成することができる。
このリアルタイム感がこれまでのCADにはなかった感覚だ。
また、ある種の「融通が効かなさ」に表れるデジタル感だ。
BIMの入力作業は、作図をするというよりもPC上で実際に建物を建てるという感覚がある。
例えば鉄骨造の自転車置場では仕上材の下地をきちんとモデリングしないと、アクソメやパースで表示したときに仕上材が浮いている状態になる。
これまでは二重線で何となく表現してしまっていたところが、BIMで設計する際にはまるでPC上のモデルからさまざまな質問を投げかけられるような感覚になる。
「ここの納まりはどうなっているの?」
「ここはどんな下地がどれくらいのピッチで入っているの?」
などと問われ、明確な答えをモデリングしなければ、平面図表示では納まっているように見えても、断面図表示では納まっていなかったというようなことがある。
つまり、BIMで設計する上では建築一般についてしっかりとした知識が必要となり、経験が浅く知識の少ない私は所々で手が止まってしまうのだ。
BIMとは正直である。
BIMには「現場合わせ」なんていうアナログ的言語は通用しないのだ。
私たちのBIMを求めて
テンプレート=財産
木製建具、アルミサッシ、キッチン、椅子、テーブル、壁仕上げ、床仕上げ等建築に関わる材料、部品を挙げるときりがないが、それらがある程度テンプレート化されているとモデリング等の時間は格段に短縮できる。
またそれらの積み重ねは設計事務所の仕様、つまり意思ともいうべきものになっていくはず。
しかし、それらを構築するには膨大な時間と労力が必要とされる。
大手組織事務所やゼネコンでの取り組みは数々のメディアにて取り上げられていて、その完成度の高さに舌を巻くけれど、彼らも膨大な時間や人工を浪費した上でシステムを完成させたはずなのだ。
つまり弱小事務所がBIMを取り入れ、それをフル活用するには時間も金もノウハウも足りない。
これからは実際のプロジェクトの中でBIMを取り入れていき、少しずつでも着実にテンプレートを作りため、事務所の財産を増やしていければと思う。
実務レベルの情報が足りない
今も少しずつではあるがBIMのスキルを上げている実感はある。
もっと上達して、近いうちに建築雑誌に載っているようなBIMモデルを利用した風や光、熱環境などのシミュレーションをどんどん試したいと思っているが、そのステップに辿り着くにはもう少しスキルアップが必要だ。
ところが、BIM入門者向けの手引き的な情報がまだまだ少なく、雑誌の紙面を飾る華やかなBIM情報と入門者の実力の間には大きな隔たりを感じる。
BIMで設計した最先端の事例やBIMの可能性といったBIMそのものの情報はインターネットや書籍でたくさん存在しているのだが、ツールの操作方法や機能といった実務レベルでの情報となると少ないのだ。
目標へたどり着くための地図がないため、日々ひたすらあがいて試行錯誤を繰り返しながら何とか少しずつ前に進んでいるような感覚だ。
将来の私を夢見ながら
BIMは2DCADと同様に標準的なツールとして広く浸透していくことだろう。
「ウチは小さい事務所で今も業務に支障はないからBIMなんて関係ない」
なんてことを言っていてはもったいない。
BIMというツールを大手組織事務所やゼネコンだけのものではなく、私たち中小事務所も積極的に取り入れていくべきだ。
その時、建築設計がどのような変革を迎え、何を魅せてくれるのか。
またその時、私たち設計者は何を見据えて設計業務に取り組んでいるのか。
非常に楽しみな世界が待っているのは間違いない。
いつの日か、自由自在にBIMを操りどんどん図面を作り出す自分の姿を夢見ながら、私は今日もあがき続ける。
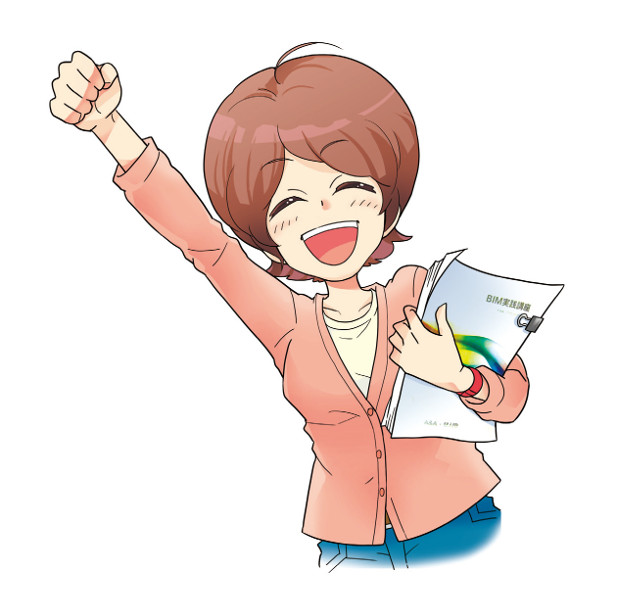
【出典】
建設ITガイド 2013
特集「建設イノベーション!3次元モデリングとBIM&CIM」