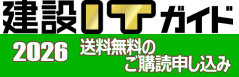熱流体解析ソフトウエア「FlowDesigner」
株式会社類設計室
所在地:大阪府大阪市(大阪本社)、東京都大田区(東京本社)
創立:1972年
資本金:9,900万円
従業員数:358名
主な事業内容:設計事業(建築の企画、計画、意匠、構造、設備、積算、
監理)、教育事業、農園事業、宅配事業、管材事業
https://www.rui.ne.jp/

設備設計部 主任 設備設計部
田所 一隆 氏 名取 茉優 氏
「スピード」「操作性」「BIMとの互換性」が導入の決め手に
株式会社類設計室の設備設計部では、施設の機械系および電気系の設計を担当している。
元々同部署では、FlowDesignerとは別の熱流体解析(CFD)ソフトで温熱環境や通風などのシミュレーションを行っていた。
しかし、近年は国などとの設計契約で「環境配慮型プロポーザル方式」が採用されるなど、環境への配慮や省エネ性を重視する機運が高まっており、より最適なツールを検討する必要性に迫られた。
田所氏と名取氏は、導入までの経緯を次のように話す。
「従来は実際に案件が動き出してからシミュレーションを行っていましたが、プロポーザルの資料で環境要素が重視されるようになり、設計業務を行いながら同時にシミュレーションもするというスピード感が求められるようになってきました。このため、ニーズにマッチする解析ソフトの導入を検討することになりました」(田所氏)
「検討段階で、プロポーザルの資料に盛り込むために実際にFlowDesignerで解析を行ったのですが、解析スピードが速く、高い精度で検証できたのが導入の決め手になりました。また私は入社以来電気系の担当で、気流や温熱解析の経験はゼロだったのですが、そんな私でも使えたというのは会社へ導入を求める際のアピール材料になりました」(名取氏)
迅速なシミュレーションを実現できる計算ソルバー、専門知識がなくても使いやすい操作性、そして使用しているBIM(AutodeskRevit)との高い互換性という3拍子がそろったFlowDesignerは、無事に同部署での導入が決定した。
FlowDesigner最大の特長は、気流や温熱環境を「見える化」できること。
顧客への提案の場面でも、その特長をいかんなく発揮する。
「スキップフロアを設けたある物件では、FlowDesignerでのシミュレーションにより空気だまりが発生することが分かりました。このため、解析結果を提示しながら『従来型の空調ではこのように空気だまりができてしまう』『原因はこれ』『だから当社では別の空調システムを提案したい』とご説明したところ、お客さまが深く納得した様子で話を聞いてくださいました。結果的に、当社の提案する内容で改めて検証してほしいという要望をいただきました」(名取氏)
技術者が考える最適な設計も、顧客に魅力や導入メリットが伝わらなければ実現しない。
FlowDesignerでの温熱環境の見える化が顧客の納得感を引き出し、より快適な空間づくりに寄与していることがうかがえる。

類設計室による、奈良商工会議所の吹抜空間(エントランス)の空調効果のシミュレーション検証。同物件は環境省が推進する「レジリエンス強化型のZEB実証事業」(令和4年度補正予算)に採択された。
社内外のコミュニケーション活性化にも貢献
同社ではここ数年DX化を推進しており、BIMでの設計をはじめ、資料のデータ化や社内コミュニケーションツールの活用なども進んでいる。
FlowDesignerもこうしたDX化の一端を担うものだが、導入によりチーム内のコミュニケーションも活性化しているという。
同社は元々「年齢に関係なく議論ができ、さまざまな価値観を認め合うことができる雰囲気がある」と田所氏は言うが、こうした企業風土にFlowDesignerはマッチした。
「シミュレーション結果が分かりやすく可視化できるため、チームでの共有もスムーズになりました。最近では解析結果もさることながら、『どのように条件を設定したの?』『この解析結果をどう捉えたの?』という話題で盛り上がることが多くなりました」(名取氏)
「解析そのものがスピーディーに行えるので、共有も気軽にできます。共有することで議論が生まれ、物件チーム全体の課題に結びつき、建築総体としての統合度をさらに高めていけます」(田所氏)
DXの浸透は、ともすれば対面でのやりとりが希薄になってしまう可能性も含んでいるが、同社でのFlowDesignerの使い方はこの対極をいくもの。
作業の省力化により本来注力すべき業務に充てる時間が増え、かつ社内のコミュニケーションも活発になるという、理想的なDXの在り方を実現している。
また、「共創」をキーワードとして社内外の異なる事業との協業を進めている同社。
設計部門では産学連携でプロジェクトを行う機会もあり、社外との関係構築にもFlowDesignerを役立てている。
「環境設計を研究している大学の先生方にはFlowDesignerのユーザーも多く、同じユーザーとして『仲間』と感じてもらえることがあると思っています。また、論文などを見るとFlowDesignerの使い方は研究者によってさまざまで、実際に使用しているからこそ学びも大きいです」(名取氏)
FlowDesignerはユーザーとのコミュニケーションだけでなく、設計者や研究者という枠を超えたユーザー同士のつながりも生み、業界発展に貢献する可能性が垣間見える。

手厚いサポートのもと情報発信や現場での活用も視野に
設備設計部では、現在名取氏を中心に年間3~5件程度の物件の解析を行っている。
解析モデルは販売元/開発元であるAKLにも共有し、シミュレーションがうまくいかない場合は相談に乗ってもらえるなど、サポート体制には大きな信頼を寄せている。
類設計室では、論文執筆や雑誌への寄稿などを通じた自社の情報発信に注力している。
FlowDesignerを用いた環境設計の実績も広く発信したい考えで、解析結果をどうアウトプットするかが今後の課題となるが、「発信の場面によって最適なアウトプットの手法は変わってくるので、AKLにはこれらのアドバイスもお願いしたい」と田所氏は話す。
また設計段階でのシミュレーションが当たり前になったことで、今後は施工現場との連携が増え、シミュレーションも高度化すると田所氏は予想しており、AKLのサポートに大きな期待をのぞかせた。

多彩な機能を追求したい
FlowDesignerには、気流のほか音響や結露といった環境設計に重要な要素のシミュレーション機能も装備されており、使いこなすことでより高度な設計提案が可能となる。
田所氏、名取氏ともに「FlowDesignerのいろいろな機能をもっと使えるようになりたい」と声をそろえ、今後のさらなる活用に意欲を見せる。
またAKLでは顧客サポートに力を入れるだけではなく、DX化を加速化させるべく未来に向けて他ベンダーとの連携を強化している。
今後は「BIMソフト上で気流シミュレーションが完了する」といった作業の効率化、一本化を見据えている。
いわば「顧客との共創」を目指しソフト間の連携性を強化するAKL。
そして開発ベンダー・顧客・大学などとの連携により「共創」を実現している類設計室には、強いシナジーが感じられる。
設立以来、顧客の声を製品に反映することを重視し、これらの蓄積であらゆる場面でのサポートを可能にしてきたAKL。
今後もユーザー企業との密な連携と、それによる製品のアップデートという好循環が期待される。
最終更新日:2025-05-28
←戻る ↑ページ上へ ↑記事一覧へ